
-
ENEOSの長期ビジョン
ENEOSグループは、長期ビジョンとして「『エネルギー・素材の安定供給』と『カーボンニュートラル社会の実現』の両立をめざす」を掲げています。水素・再エネ・合成燃料・CCSを推進し、安定性・経済性・環境性のバランス(S+3E)を保ちながら社会のエネルギートランジションを主導し、2050年度までにScope1+2排出ゼロをめざします。
-
研究所の役割
中央技術研究所では「今日の当たり前」を支えるためにエネルギー・素材の安定供給のための研究を行っています。一方で「明日の当たり前」のため、再エネ由来の電力を、貯蔵・輸送に適した物質に変換する「水素キャリア製造技術(Direct MCH®)」や「合成燃料・バイオ燃料」などの技術開発も進め、社会実装をめざしています。研究開発ではAIやMIなどのデジタル技術を駆使し、開かれた研究環境のもとでオープンイノベーションを推進しています。
-

中央技術研究所長
田中 祐一
1995年入社。精製プロセス操業支援、水素供給インフラ、GTL実証などの研究に従事。技術戦略室副室長、技術計画部副部長、IT戦略部長などを経て現職へ。要素技術を社会実装に繋げるスケールアップエンジニア。天職はマネジメント。モットーは「すべてのメンバーが楽しく働くことで成果は最大化できる」。
-

中央技術研究所 フェロー
佐藤 康司
1994年入社。2001年より家庭用燃料電池「ENE FARM」開発に従事。その後、水素、電解、CO2利用などのカーボンニュートラル研究マネージャー、先進技術研究所長、中央技術研究所長を歴任して現職(フェロー)へ。再エネから水素キャリア直接製造Direct MCH®の発案者。現日本エネルギー学会会長。モットーは「ダメでもめげない」。
-
 Interviewer
Interviewer
Interviewer
Interviewer中央技術研究所 技術戦略室
A.N.
-
CHAPTER 01
ダブルリーダー体制の狙い
2025年4月、中央技術研究所では、マネジメントと技術、
それぞれの専門性を担う2人のリーダーによって機能強化を図る新たな体制がスタートしました。
各リーダーの役割やその狙いをご紹介します。A.N.
2025年4月に田中さんが所長に就任し、中央技術研究所は田中所長と佐藤フェローのダブルリーダー体制となりました。その狙いと役割を教えてください。
田中
私の役割は所長として組織内のコミュニケーションおよび人材リソースの活用といったマネジメントです。所員の自己実現を支え、いいパフォーマンスを引き出すためにはマネジメントのプロフェッショナリズムが必要です。一方で研究所の技術力を発揮するには、高度な知識を持ち研究を前に進めるリーダーシップも重要です。これを役割分担し、得意な領域を担い協力することで研究所のパフォーマンスを最大化することが狙いです。
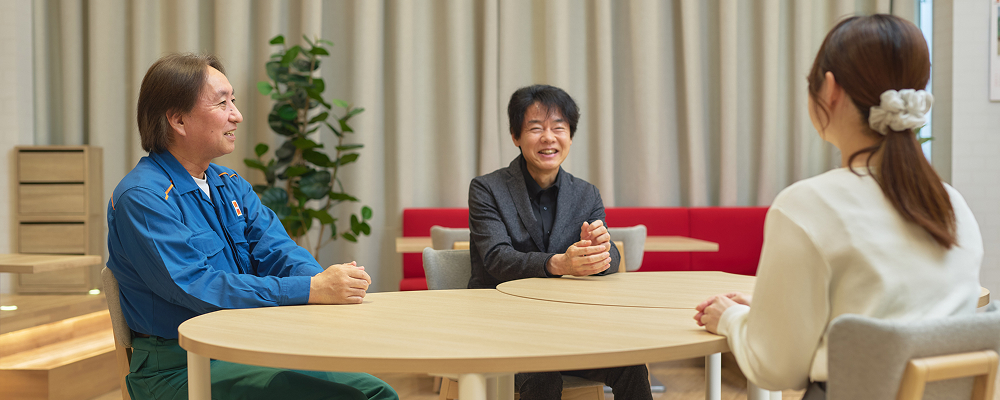
佐藤
マネジメントは田中さんに任せ、私は研究者としてのキャリアを活かして技術面からのサポートに徹することができます。学会の委員なども多数やっており、外部とのネットワークを自社の研究推進にも活かしています。
田中
研究フェーズをより商業化に近づけるためには、臨機応変に組織を改変するマネジメントが必要になります。ダブルリーダー体制にはENEOSが取り組む様々な研究を深化させると同時に、社会実装を加速する狙いもあります。
-
CHAPTER 02
中央技術研究所を導く"2つの視点"
異なるバックボーンを持つ2人のリーダーが、それぞれのキャリアで培った知見や経験を活かし、新体制を推進。
研究所の強みを引き出す役割分担とその背景に迫ります。A.N.
ダブルリーダー体制を進めるに当たって、それぞれのキャリア、バックボーンがどのように活かされているのでしょう?
田中
私のキャリアは石油精製装置の改良からスタートしました。実証エンジニア、スケールアップエンジニアが私の本分です。その後は研究所内外でDXに携わり、直近はIT戦略部長として社内業務の変革を担当するなど、自身の専門とは異なるフィールドでマネジメントに関する経験を重ねてきました。中央技術研究所長として、私はマネジメントのプロフェッショナルとしてのキャリアと知見を活かし、研究所のパフォーマンス向上を考えていきます。
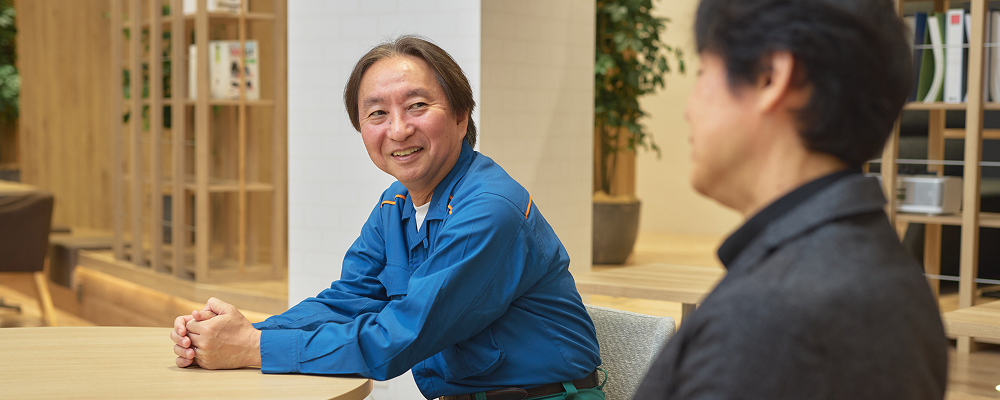
佐藤
私は入社して以来、ずっとこの研究所で勤務しています。燃料電池の開発に携わり、そこで培った知見を基に水素やCO2利用などの研究に従事してきました。その中で得た社内外の人脈は私の大きな財産です。培ったネットワークから最新の情報や技術トレンドをキャッチアップし、個々の研究テーマをサポートすることが、フェローとしての私の役割だと考えています。
-
CHAPTER 03
中央技術研究所のミッション
カーボンニュートラルとエネルギー安定供給の両立という長期ビジョンの実現に向けて、
中央技術研究所はどのような貢献を果たすのか。その使命と展望をご紹介します。A.N.
ENEOSグループの長期ビジョンの達成に向けて、中央技術研究所はどのような役割を果たしていくのでしょうか。

田中
日本で排出される約10億トンの温室効果ガスのうち、ENEOSは2億トンに関わっており、ENEOSこそが低炭素社会の実現を考えていく責任があります。近年、エネルギー・素材をめぐる国際情勢は不確実性が高まっています。技術を中長期的にスケールアップする間には追い風も吹けば向かい風も吹くでしょう。その中で、研究所は目先の動きに惑わされることなく、地にしっかり足をつけて研究を前に進めていくことが大事です。カーボンニュートラル実現の目標に向けて、やるべきことをやり続けていく所存です。
佐藤
私たちの研究には「今日の当たり前」を支えるための研究と、「明日の当たり前」をリードするための研究があります。これから事業化される研究には長期的なビジョンが不可欠です。カーボンニュートラルを実現するには、合成燃料のような今はまだないテクノロジーを生み出し、社会実装に結びつけなくてはなりません。社会課題に立ち向かう広い視野を持ちつつ、ENEOSにとっても次代の収益の柱を生み出せる、そのような研究の進め方ができるのが、ENEOSの中央技術研究所です。
-
CHAPTER 04
中央技術研究所の主要な取り組み
カーボンニュートラル実現に向けた4つの重点研究テーマに加え、
AIやMIなどの先端技術を取り入れた研究手法にも注力。進化を続ける研究所の今に迫ります。A.N.
現在、中央技術研究所が特に力を注いでいる研究テーマを教えてください。
佐藤
温室効果ガス排出削減に向けて取り組んでいるテーマが4つあります。「水素キャリア製造技術(Direct MCH®)、「合成燃料」、「ケミカルリサイクル」、そして「バイオ燃料」です。これらはプロジェクトの実証段階に入っており、商用化への道筋が見えてきました。
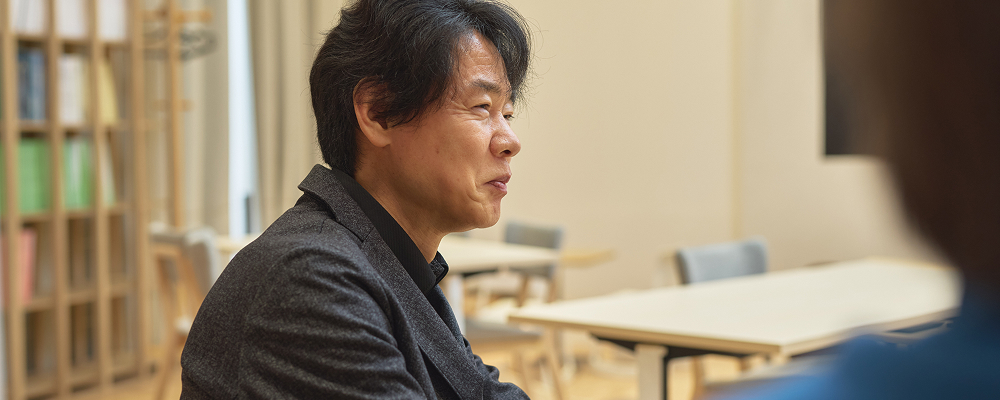
A.N.
研究の進め方、手法についてはどのような特色がありますか?
田中
近年の研究開発は最新テクノロジーの動向をキャッチアップし、取り込み、使い倒していくことが不可欠です。我々もマテリアルズ・インフォマティクス(MI)やAI、最新の分析・解析技術を積極的に活用し、効率的な研究を進めています。
佐藤
もはやすべてを「実験」するラボはありません。触媒や高分子、潤滑油の添加物探索にはMIが利用されており、これまでの常識では考えもしなかった物質が候補に挙げられるようになりました。MIは研究の進め方だけではなく、発想や視点も大きく変えています。デジタル技術の活用は、今後の研究開発においても重要なポイントになるでしょう。
-
CHAPTER 05
研究所が求める人物像
中央技術研究所の力を引き出すのは、多様な専門性と柔軟な発想力を持つ人材たち。
最後に、ENEOSならではの成長機会と研究者としてのやりがいに触れていきます。A.N.
中央技術研究所がその使命を果たすには、どのような人材が必要だと考えますか?
佐藤
研究には様々なフェーズがあります。そして、研究者にも各フェーズに対しての向き不向きがあります。そうした多様性に富んだ人材が研究所には必要で、多彩な人材がいてこそ研究所は総合力を発揮すると私は考えています。
田中
自分の専門を柱に持ちつつ、活躍すべき領域が広がることを積極的に捉えるマインドがあるといいですね。一つの技術だけで社会に貢献する仕事はできません。自身の専門をビジネスとして開花させることにも興味を抱き、積極的にチャレンジして欲しいです。また、近年の研究開発にはデジタル技術が不可欠ですから、AIに限らず、新たなデジタル技術を使い倒していって欲しいです。一方でAIでは取って代われないことをする人も同様に必要です。本当に新たな発想は人間からしか生まれませんから。
A.N.
ENEOSで働く魅力、おもしろさはどこにあると思いますか?
佐藤
様々な専門家が垣根を越えて気軽に相談できる環境が整っており、それぞれの持ち味、強みを活かせるところでしょう。2026年度には新たな研究棟が完成しますが、そこではワンフロアにすべてのメンバーが集い、自由闊達に交流することで知の融合を図り、新たな価値を創造します。また、他企業や研究機関の方と交流するスペースも設け、オープンイノベーションも促進します。
田中
やりがいも大きいと思います。先に触れたようにENEOSはエネルギーのメインプレイヤーであり、カーボンニュートラル実現に当事者として関わることができます。研究者冥利に尽きます。またキャリアパスも多彩です。明日のシーズを探す人、育てる人、事業化する人、そんな多様な人材を育成するために、個々の適性・志向に合わせたビジネスタイプ、オーソリティータイプのキャリアパスを用意しています。
